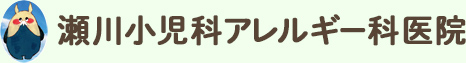2025/04/30
第61回日本小児アレルギー学会学術大会が会長:伊藤 浩明 先生(あいち小児保健医療総合センター)「Science Based Allergology 科学に根ざしたアレルギー学」というテーマで「名古屋コンベンションホール」で開催されました。開会式から閉会式まで参加し楽しむことができました。今回のテーマは「科学に根ざしたアレルギー学:Science Based Allergology」です。会長の伊藤 浩明 先生は、アレルギー疾患は、環境や衣食住といった「体の外」に直接的な原因を持ち、その対策も病院における「治療」に留まらず、生活や社会全体のあり方に直接関係しています。主に「体の中」を扱う狭義の医学から見たら、特殊な疾患とも言えるでしょう。そのため、ここでイメージしているScienceとは、必ずしも医学という領域に留まらず、農学・食品化学・栄養学・環境学・教育学・人文科学など幅広い領域の学問です。よりよい治療法を選択することを目的とした、臨床医学における狭義の「エビデンス」に留まらず、アレルギー疾患を少し外側から考えることで、皆様にとって新しい発見のある学術大会になるよう取り組んでいます。
経口免疫療法(OIT)の最先端:日本と海外の違いについて 国立病院機構相模原病院臨床研究センターより永倉 顕一先生より話しがありました。日本の免疫療法は、海外にくらべ研究対象の選択、方法もしっかりしていて、結果は信頼できるものと考えられます。経口免疫療法(OIT)は、国内外での取り組みにより安全性は向上していますが、短期的 には耐性獲得(自由に摂取が可能)の達成は期待しにくく、研究終了後も症状や課題が残存する可能性があることです。長期の治療継続を前提とした児と保護者への対応が必要とのことでした。
「食物アレルギー発症予防:「早めに食べる」だけでは不十分」 社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院 崎原 徹裕先生より話しがありました。2010 年代後半からの“早期摂取”によるアレルギーの発症を予防するためにはアレルゲン食物の“早期摂取” のみでは不十分で、“定期的な摂取の継続”が重要であることのはなしがありました。いつまで続ければ良いかと言うことは、アレルギーの発症リスクの低い方、アレルギー発症のリスクの高い方と分けて考えていく必要があると思われますが、どのくらいの量をいつまで摂取したらよいかは現在解答がでていません。
大阪母子医療センター呼吸器・アレルギー科の錦戸 知喜先生より「喘鳴を認める患者の鑑別診断」の講演がありました。ガイドラインの話しではなく、経験した間違いやすい症例の話しでした。気管支喘息は最も頻度の高い小児の慢性呼吸器疾患で咳嗽、喘鳴、呼吸困難を反復する症例で喘息を考えるのは妥当な判断ではあるが、呼吸器症状を反復する疾患は多岐にわたる事を忘れてはならない。
気管支軟化症は喘息の急性増悪(発作)と同様に感冒を契機に比較的高調性の喘鳴を反復するため、症状は喘息に非常に類似しています。やはり当初は喘息と診断されるが多く、吸入ステロイドがよく使用されています。このような症例で吸入ステロイドは増悪因子となる可能性もあり、ステロイドの反応性が悪い場合は、速やかに診断名を再考する必要があるとのことでした。
二日間で参考になることが非常に多かったです。今後の臨床に活かしていきたいと考えます。