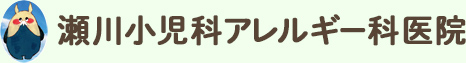2025/06/17
第25回食物アレルギー研究会が2025年2月9日(日)の現地開催、会長:三浦 克志先生(宮城県立こども病院アレルギー科 科長)にてパシフィコ横浜アネックスホールにて開催されました。開会式から夕方の閉会式まで、一日食物アレルギーについて勉強する機会を得ることができました。
午前中は 特別プログラムI
「急増する木の実類アレルギーへの対応」が行われました。
1.木の実類アレルギーの現状
海老澤 元宏(国立病院機構相模原病院臨床研究センター)先生より、2023年の即時型の食物アレルギーの統計でナッツ類が牛乳を追い越し、鶏卵の次に多い、第二位となったことの報告がありました。
2.加工食品のアレルギー表示と中食・外食における対応
野中 ひとみ 先生(シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社)より講演がありました。ファミリーレストランなどの中食には、食物アレルギーの表示義務がないので、誤食に注意する必要があるとのことでした。
3.栄養教諭の考える学校給食における対応
〜堺市における食物アレルギー対応と栄養教諭等を対象とした木の実類アレルギー調査の結果より〜松田 由紀恵(堺市立東百舌鳥小学校の)先生より話がありました。
4.木の実類の発症予防・治療の可能性
伊藤 浩明(愛知小児保健医療総合センター)先生は、昨年学校給食の同じ給食でカシュナッツアレルギーが二人発症し、一人は重症化し集中治療室に収容4回のアドレナリン投与後後アドレナリンを点滴静注した話がありました。愛知県では昨年アナフィラキシーが5人出て、そのうちの4人がカシュナッツでしかも4人とも初めてのカシュナッツ摂取とのことでした。こういう事例をみると給食からナッツを除去するのが良いと思われますが、すでに除去している自治体も多くあると思われます。
〇特別プログラムII
「食物アレルギー診療はどこまで進んだか」が行われました。
1.アレルギー疾患医療拠点病院の取り組み「宮城県の場合」
三浦 克志 (宮城県立こども病院)先生より話しがありました。
2.発症予防:抗原摂取と湿疹への抗炎症治療
崎原 徹裕 (ハートライフ病院)
食物アレルギーの予防は、早期発症の湿疹に対しては、積極的に抗炎症外用療法を行う必要性、早期摂取だけではなく、摂取後定期的な摂取が必要であるとのことでした。
3.食物アレルギーの特殊型:食物蛋白誘発胃腸炎(FPIES)とその類縁疾患
森田 英明 (国立成育医療研究センター)
食物摂取後1時間移行に嘔吐を認める、食物蛋白誘発胃腸症が増加している。
鶏卵は2歳で約半数が、牛乳は3歳で、魚は6歳で摂取可能となることが多い。
4.食物経口負荷試験と食事指導
杉浦 至郎 (あいち小児保健医療総合センター)
5.免疫療法
柳田 紀之 (国立病院機構相模原病院)先生が講演されました。
一日食物アレルギーにどっぷりつかり今後の臨床に活かしたいと思います。