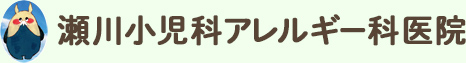2025/11/20
第11回総合アレルギー講習会が2025年3月22日~23日に、神戸国際会議場・神戸ポートピアホテルにて会頭海老原伸行先生((順天堂大学医学部附属浦安病院眼科)にて「Total Allergistをめざして」のテーマの元に開催されました。
会頭海老原伸行先生の述べていることが素晴らしくここに掲載させて頂くこととしました。
アレルギー疾患の患者数は年々増加しており、本邦では全人口の約2人に1人が何らかのアレルギー疾患に罹患している状況です。アレルギー疾患は診療科・臓器横断的に発症するため、内科、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科の医師が連携して診療にあたる必要があります。しかし、それぞれの科のアレルギー専門家の集団のみでは、多臓器にわたりアレルギー疾患を罹患しているアレルギー患者を全人的に治療・管理するのは困難です。また、2014年にアレルギー疾患対策基本法が施行され、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーの6疾患について、重症化予防、症状の軽減、患者様の生活の質の向上や医療の均てん化のため、各都道府県にはアレルギー疾患医療拠点病院が設置されました。しかし、地方都市においてはまだまだアレルギー専門医の数が不足するところも多く、全国レベルでのアレルギー疾患医療の均てん化は道半ばにあります。以上の背景・状況を鑑みますと、Total Allergistの育成が重要になります。
Total Allergistになるには、アレルギー疾患の病態全般を理解する知識と、基盤5領域(内科・小児科・皮膚科・耳鼻咽喉科・眼科)の必須の知識と基本的な診断・治療技術の修得が必要です。具体的には、各科の代表的なアレルギー疾患の診断・治療技術、原因物質の回避・除去指導、ステロイド薬・抗アレルギー薬・分子標的薬・生物学的製剤の使用法、アレルゲン免疫療法(皮下・舌下・経口)の実践などの修得が必要です。しかしそれらを個人の努力で修得することは不可能です。そこで、豊富な内容をより効率的に修得することが可能な総合アレルギー講習会が誕生しました。2014年に第1回講習会が始まり、2025年で第11回を迎えます。毎回、専門科を問わず多くのアレルギーに興味のある先生方、パラメディカルの皆様の参加があります。
総合アレルギー講習会では、講義では自分の基盤領域以外のアレルギー学も広く学べ、実習では診療に必要な技術とノウハウを体験できます。これからアレルギー専門医を取得する方には必須の講習会であると同時に、アレルギー診療に携わるすべての医療従事者に学んで頂ける場となっています。
今回も、講義の多くはハイブリッド開催(後日オンデマンド配信)、実習は現地参加を予定しています。オンラインは便利でじっくり視聴できる利点もありますが、一流の講師のオーラに触れ、全国の仲間と交流できる点で、現地参加はやはり他に替え難いものです。
1.Year in Review 食物アレルギーの発症予防
二村 昌樹(国立病院機構名古屋医療センター小児科)の講演です。
食物アレルギーの発症予防の、エビデンスの有無について述べています。
湿疹予防目的の保湿剤塗布、湿疹治療後の鶏卵の早期摂取、ピーナッツの早期摂取は思春期までのピーナツアレルギーの発症予防、早期からの積極的な湿疹治療、は必ずしも予防ができないと述べています。この結論には、異論もあると考えます。
2.吸入性アレルゲンコンポーネント
福富 友馬(国立病院機構相模原病院)
五大吸入性アレルゲンは、ダニ(ヤケヒョウダニ)、ペット(犬、ネコ)、真菌(アルテリナリア、アスペルギルス)、昆虫(ガ、ゴキブリ)、花粉(杉、ヒノキ、カバノキ科、)です。
最近のペットの飼育について述べています。
ペットアレルギーの特徴は、ペットアレルゲンは(特にネコ)環境に浮遊しやすい。飼育者は多量のアレルゲンに暴露。非飼育者も暴露、感作、症状を来しうる。生後3ヶ月までの飼育では免疫寛容が生じる可能性。感作患者が飼育するとアレルギー重症化危険因子になりやすい。アナフィラキシーや大発作のリスクあり。飼育継続により部分的な免疫寛容可能性があるとのことです。
3.Year in Review 小児食物アレルギー
髙橋 亨平(国立病院機構相模原病院臨床研究センター臨床研究推進部疫学統計研究室)
Ladderについて述べています。
Ladder とは食物アレルギー児の自宅での段階的に増加していく導入療法です。
それが安全かどうか検討していますが、171例中73例(42.5%)に症状が誘発されていて、日本での段階的経口負荷試験の方が安全にすすめることができると述べています。
2日間、開会式から閉会式まで楽しく、勉強ができました。
今後の臨床にいかしたいと思います。